本書『メノン』は、古代ギリシアの哲学者プラトン(紀元前428頃~紀元前347頃)の対話篇だ。『ソクラテスの弁明』といった初期対話篇と、『国家』といった中期対話篇をつなぐ位置を占めている。
本書のテーマは「徳とは何か?」というものだ。対話はソクラテス、青年メノン、政治家アニュトスの間で行われる。
冒頭、メノンがソクラテスに対して次のような質問を投げかける。
こういう問題に、あなたは答えられますか、ソクラテス。—人間の徳性というものは、はたしてひとに教えることのできるものであるか。それとも、それは教えられることはできずに、訓練によって身につけられるものであるか。それともまた、訓練しても学んでも得られるものではなくて、人間に徳がそなわるのは、生まれつきの素質、ないしはほかの何らかの仕方によるものなのか……。
「徳」は教えられるか。それとも、ただ訓練によってのみ得られるのか。あるいは生まれつきの素質によるのか。こうメノンは問う。以降の対話は、この点をめぐって行われる。
メノンの問題提起に対して、ソクラテスは、私は徳が何であるかについて全く知らない、というように“とぼけて”、ぜひ君の説を聞かせてくれ、とメノンに尋ねる。
徳の「本質」を教えてくれ
メノンは次のように答える。
男の徳は国事をよく処理すること、女の徳は家事を上手にこなすことです。子どもには子どもの徳が、老人には老人の徳がある。それぞれが成しとげるべき仕事に合わせて、1人ひとりの人間に応じた徳があるのです。
しかしソクラテスはメノンの答えに満足しない。なぜならソクラテスの求めている答えは、もろもろの徳に共通する、徳の本質だからだ。ソクラテスは次のように言う。
「たとえその数が多く、いろいろの種類のものがあるとしても、それらの徳はすべて、ある一つの同じ相(本質的特性)をもっているはずであって、それがあるからこそ、いずれも徳であるということになるのだ。この相(本質的特性)に注目することによって、「まさに徳であるところのもの」を質問者に対して明らかにするのが、答え手としての正しいやり方というべきだろう。」
しかし、ソクラテスの意をメノンは上手く理解することができず、なかなか議論がかみ合わない。メノンは混乱してしまう。
魂の想起説
ここでメノンはソクラテスに対して、次のような根本的な疑問をぶつける。
ソクラテス、あなたは徳は何であるか知らないと言う。しかしもし徳について何も知らないのであれば、どうしてそれを探求することができるのでしょうか。
これに対してソクラテスは、そうした反論はナンセンスだと答える。
なぜなら人間の魂は不死だから、見聞きしたことのない事柄は存在しないし、それぞれの事柄は本質的にすべて関連しているので、ある事柄を「想起」(アナムネーシス)することによって、すべての事柄を学ぶことが可能であるからだ。
学ぶとは魂が前世で経験したことを思い出すことである。想起によって、意識されずにとどまっていた「思わく」が取り出され、「知識」として定着する。したがってもし徳が知識であれば、徳は教えられるものであるだろう。
これがいわゆるプラトンの想起説だ。
徳は教えられないのでは?
ここで、アニュトスが議論に加わる。ソクラテスは、アニュトスに対して次のように論じる。
もし徳が教えられるものであれば、徳の教師がいなくてはならない。その候補としては、ソフィストもしくは徳のある人をあげることができる。しかし両者ともきわめて疑わしい。ソフィストは若者を堕落させるので話にならない。一方、徳のある人が徳を教えられるのであれば、かの歴史家トゥキディデスはソフィストを雇う代わりに、誰か徳のある人を見つけ出してきたに違いない。そうである以上、徳は教えられないと言うべきではないだろうか?
徳は知識である
そこでソクラテスは観点を変え、徳を導き手としての側面から論じる。
善き人間は徳をもち、有益な人間であることから、徳を有益なものと規定する。しかし、それが有益であるためには、正しく用いられるのでなければならない。したがって、正しく導かれた徳こそが有益であり、それゆえ知識でなければならない。
正しく導くのは知識だけ?
しかし、ここでソクラテスは立ち止まり、次のように問う。
何かを正しく導くことができるのは知識だけなのか?正しい思わくもまた導き手としては知識に劣らないのではないか?
正しい思わくは、原因(根拠)の思考によって想起し縛りつけることによって知識となる。永続性をもっている点で、知識は正しい思わくよりも価値をもつ。
ただし、行為の結果に関してみれば、知識と正しい思わくの間には違いはない。徳が教えられない以上、正しく導くのは知識ではなく、正しい思わくだ。であれば、国家を正しく導く政治家は“神がかり”にかかっていると言うべきだ。
とはいえ本当に明確なことは、徳それ自体がそもそも何であるかを明らかにしてから分かるはずだ。
そう言い残して、ソクラテスは議論の場から立ち去ってしまう。
徳の本質を問う態度が画期的
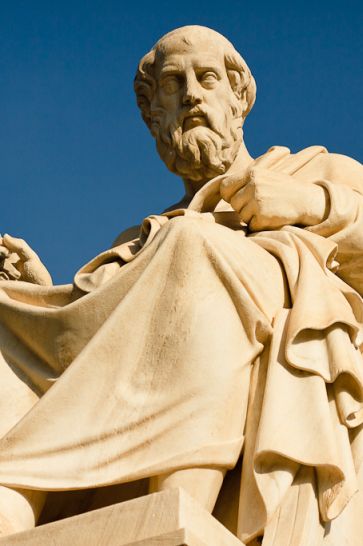
本篇でプラトンは、徳の属性を論じつつも、結局その本質は示しておらず、消化不良の感がある。強弁が目立ち、核心に到達しているとは言いがたい。
とはいえ、プラトンの議論が画期的だったことは確かだ。習俗の力が近代よりもはるかに強かった時代に「何が徳の本質だろうか?」という問題を立てたこと自体、評価すべきポイントだと言えるだろう。
プラトンは『パイドン』や『国家』にて、イデア(真実在)説を展開している。そこでは、イデアが価値の“本体”、根拠として位置づけられている。本篇はイデア説が成立する以前の作品であり、プラトンの主著には数えられていないが、本質という概念の普遍性の観点からすれば、参考とすべきところがある。とりわけ数学が広範な普遍性をもつ条件については、ここで示されている本質の概念が一定の答えを与えていると言うことはできるはずだ。
- Carlos Blanco (CC BY-NC-SA 2.0; modified)
- Carlos Blanco (thumbnail, CC BY-NC-SA 2.0; modified)
