箇条書きで解説しました。急ぎの方はこちらからどうぞ → ミル『自由論』を箇条書きで要約する

本書『自由論』(1859年)はイギリスの功利主義者ジョン・スチュアート・ミル(1806年~1873年)の代表作だ。
本書のテーマは、その名の通り、自由だ。ただ自由といっても、これは意志の自由ではなく、「市民的自由」、つまり市民社会における自由のことを指している。
ミルは本書で、個人が社会においてもつ市民的・社会的自由の本質は何か、そして個人の自由がどの程度まで正当に制限されうるかについて考察している。
自由を個人的な意志(善をめざす自由)の問題として捉えるか、もしくは人びとの関係性において実質化されるものとして捉えるか。これがカントとヘーゲルの分岐点となっている。本書でミルが取っているのはヘーゲル的な視点だ。
功利主義の観点から自由を擁護する
ミルは本書で、自由について論じるための原理として「功利性の原理」を置き、これに基いて自由の本質論を展開する。
ミルは基本的に自由を擁護する立場に立つが、何もそれはミルが単に「自由であればあるほどいいことだ」と考えているからではなく、自由が功利性の原理にかなうものであり、一般的功利であると考えているからだ。
なぜ自由を原理から論じなければならないのだろうか?この点について私なりに答えてみると、それは原理を置くことによって普遍的な判断基準を確立することができるからだ。
原理を置くことで初めて、社会が自由でなければならない理由や、自由が許容される範囲とその限界について論じることができる。もしそうした原理がなければ「なぜ殺人や窃盗の自由は認められないのか?」といった極限的な問いに対してきちんと反論することができない。それでは自由論とは言えない。
功用とは無関係なものとしての抽象的な正義の観念から、私の議論にとっていかなる利益が引き出されようとも、私はその利益を抛棄するつもりであることをのペておくのが適当であろう。私は、功用を、すべての倫理的問題に関する究極的な人心に対する訴えであると考える。しかし、その功用とは、進歩する存在としての人間の恒久的利益を基礎とする、最も広い意味における功用でなくてはならない。このような恒久的利益に照らして見るときに、 … もしも何びとかが他人に有害な行為を行なうならば、それこそ、あるいは法律により、あるいはまた法律上の刑罰の適用が安全でないときには公衆の非難によって、彼を処罰する、一応の証明ある事件である。
自由とは単に制限からの解放を意味するのではない。だから何をしてもいいということではない。他者の功利を不当に損なうような行為は、法律または世論によって制限し、刑罰を与えることができる。この点については『功利主義論』でも論じられていた。
『功利主義論』はこちらで解説しました → ミル『功利主義論』を解読する
いちおうまとめておくと、『功利主義論』のポイントは、大体次のような感じだ。
これまでの正義論では、どれだけ正義を便宜から切り離せるかという点に重点が置かれていた。
しかし正義とは「一般的功利」、つまり万人にとっての功利のことだ。
人間の行為の究極的な目的は、幸福な生を享受することにある。したがって行為の正しさの判断基準は、それが人間的快楽=幸福を促進するかどうかにある。幸福を生み出すほどその行為は正しく、そうでないほど正しくない。
このことは統治についても当てはまる。つまり統治は一般的功利を向上させる限りにおいて正当だといえる。一般的功利を低下させるような統治は不当であり、妥当性をもたない。
ただし、政府が幸福の内実を一義的に規定して、それを人びとに押しつけることは容認されない。むしろ政府は、人びとの自分固有の幸福を追求する営みを持続的に発展できるような条件(インフラ)を整備することに集中するべきだ。というのも、人びとは良心と他者に対する共感をもっているので、そうした基礎さえ整っていれば、おのずと多様な幸福追求ゲームを営むはずだからだ。
自由=幸福追求ゲームを営むための自由
私たちの一切の行為の目的は幸福を得ることにある。したがって一切の行為は幸福を追求する限りにおいて正当である。統治も同様だ。一切の政治行為・政策は、多様な幸福追求の営みを下支えする限りで正当であり、一般的功利を促進する限りで正義にかなっている。
こうした功利主義的観点が、ミルの自由論を支えている。
自由の名に値する唯一の自由は、われわれが他人の幸福を奪い取ろうとせず、また幸福を得ようとする他人の努力を阻害しようとしないかぎり、われわれは自分自身の幸福を自分自身の方法において追求する自由である。
ミルが自由を擁護するのは、それが多様な幸福追求ゲームを促進する限りにおいてだ。言い換えると、私固有の幸福を、他者が幸福を獲得することを妨げないかぎりにおいて追求する自由、これがミルのいう自由だ。したがってミルからすれば、正当な理由なく他者に危害を加えることについて自由は存在しない。
この意味で、ミルのいう自由は単に「他人に迷惑をかけないこと」なのではない。もちろん他人に干渉せず、また干渉されずないことも自由の概念のうちに含めていたはずだが、それは一側面であって、中心ではない。ミルはむしろ、他人は私自身が幸福を追求するために重要なパートナーになりうると考えていた。
万人が好き勝手に幸福を追求するとエゴイズムの相克が生じてしまう。それでは自由な幸福追求ゲームは成立しない。だから正当な理由である場合を除いて、他人の幸福追求を抑圧するような行為は排除されなければならない、という順序なのだ。
万人が自由に自分固有の幸福を追求し、かつ享受している状態、これをミルは最大幸福状態と呼ぶ。
一切の統治は、最大幸福状態を実現するように方向づけられていなければならない。統治の課題は、この状態が達成できるような基礎条件を整備することにある。したがって統治は必然的に自由主義体制とならざるをえない。これがミルのポイントだ。
「多数者の圧政」と「危害原理」
ただし、ミルからすると、自由主義的な統治体制は、最大幸福状態を実現するための一条件でしかない。なぜならミルによれば、自由が問題となる領域が、国民と政府の間から、国民内部における多数者と少数者の間へと次第に移ってきたからだ。
「多数者の圧政」への対策が必要だ
いまや政府と国民の間では、自由はほとんど問題とならない。それよりも、国民の内側に政府の抑圧に代わる新たな抑圧、つまり「多数者の圧政(暴虐)」が見られるようになってきたことが問題だ。そうミルは考える。
これまで自由と権力の問題は、国民と政府の関係において論じられてきた。その際、自由とは統治者の圧政から守られることを意味していた。その解決策として、政治的自由を確保すること、また、統治者からの圧政を憲法によって抑制することが求められていた。
しかし現代になって状況は変わった。統治者の利益と意志が、市民の利益と意志であることが求められるようになった。政府は市民から権力を委託され、これを代表する。政府の意志が市民の意志と食い違えば、政府は解任され、新たに別の政府が選出される。こうした制度を確立することで、市民は政府による圧政を阻止し、自由を享受することができるようになった。
しかしここで次第に矛盾が現れてきた。つまり政府ではなく市民が市民自身を不当に抑圧するという事態が生じてきたのだ。
私は上で「市民の意志」と言った。しかしひとくちに市民の意志といっても、それが本当に各市民の意志に基づいているとは限らない。むしろそれはしばしば「私たちの意志こそ市民全体を代表している」という大声に影響されてしまい、市民の一部分、少数者に対して抑圧的に働いてしまうのだ。
私はこうした状態を「多数者の圧政」と呼びたい。
もちろん今でも、政府の権力を制限し、政治活動を常にチェックしておく必要がある。これは言うまでもない。しかしそれと同時に、多数者による少数の市民に対する不当な抑圧についても何らかの対策も行う必要があることも確かなのだ。
人民の意志は、実際には人民の最多数の部分または最も活動的な部分の意志だということになる。すなわち、大多数者、または自己を大多数者として認めさせることに成功した人々の意志を意味している。それ故に、人民は人民の一部を圧制しようと欲するかも知れない。そして、かような圧制に対して予防策の必要であることは、他のいかなる権力の濫用に対する場合とも異なるところはないのである。
今や政治的問題を考える場合には、「多数者の暴虐」は、一般に、社会の警戒しなくてはならない害悪の一つとして数えられるに至っている。
危害原理
ミルは、その対策の方針として、個性の形成を社会的圧政から保護することが必要だと主張する。ここでミルが提案するのが危害原理だ。
多様な幸福追求ゲームが自由に営まれるためには、第一に、行為は法律もしくは世論によって規制されなければならない。
しかし、しばしばそのルールは、個人または多数者の趣味(好み)に基いてしまう。なのでルールの規準をどこに置くかについて規定しておく必要がある。
そのための原理として、私は「危害原理」を提示したい。
その原理とは、人類がその成員のいずれか一人の行動の自由に、個人的にせよ集団的にせよ、干渉することが、むしろ正当な根拠をもつとされる唯一の目的は、自己防衛(self-protection)であるというにある。また、文明社会のどの成員に対してにせよ、彼の意志に反して権力を行使しても正当とされるための唯一の目的は、他の成員に及ぶ害の防止にあるというにある。
くたばれコント
ある行為が、私もしくは他のメンバーが幸福を追求するための基礎条件をおびやかす場合は、その行為を規制することには正当性がある。同様に、あるメンバーが他のメンバーに危害を及ぼさないよう防止する限りにおいて、権力の行使には正当性がある。
これを逆に言うと、そうした事態が生じないような場合において個人を抑圧することは、まったく不当なことだ。そうした事例は特にオーギュスト・コントの思想のうちに見つけることができる。
コント氏の如きは特にそうであって、彼の実証的政治学体系(Systeme de Politique Positive)の中に展開されている社会組織は、個人に対する社会の専制を確立することを目的とするものであり(法律的な手段よりも、むしろ精神的な手段によってではあるが)、しかもその専制は、古代の哲学者の中で最も厳格な戒律主義者であった人の政治的理想の中に考えられていた如何なるものをも、凌駕するほどである。

コントは『実証精神論』のうちで、実証的精神が社会連帯・統合を可能にする原理としての役目を果たさねばならないと主張していた。近代社会では知的、道徳的な無秩序(アノミー)が生じている。実証的精神がそれを解決するための唯一の道であり、そこで重要な役割を果たすのが、精神的な権威による介入すなわち道徳教育である、と。ミルのいう「精神的な手段」とはこのことだ。
コントの一連の議論は反動形成にすぎない。なぜなら根本的な問題は、いかにして最大幸福状態の可能性の原理を置くことができるかにあるのであって、アノミーの解決それ自体が最終的なゴールではないからだ。ミルが言わんとするのはそういうことだ。
『実証精神論』はこちらで解説しました → コント『実証精神論』を解読する
個性を開花できる社会へ
社会の専制ではなく、個人が自由に自分固有の幸福を追求できる社会を作り上げること、これがミルのポイントだ。
ミルはそのための条件として、「個性の開花」が必要だという。
多様なライフスタイルが存在することは、私たちにとって有益だ。伝統や慣習が行為を規制する場合、そこでは私たちの幸福の一要素が欠けてしまっている。
各人がそれぞれの個性を育て上げることで、私たちの生活は豊かになり、個人は他者にとっても価値をもつようになる。そして、他者にとって価値あるようになることで、生は一層充実する。
自分にとって不快だからといって個人を抑圧することは、価値あるものを何ら成長させない。それゆえ、いまこそ個性の権利が主張されなければいけない。差異の存在そのものが有益であることを理解しない限り、個性はますます抑圧されてしまうはずだ。
個性こそ豊かな生の条件であり、他人にとって有益で価値ある人間となるための条件だ。他人に損害を与えないにもかかわらず個性の開花を抑圧することは、功利性の原理から見て根拠をもたない。そうミルは言うわけだ。
自分にとっての「幸福」を規定する能力を
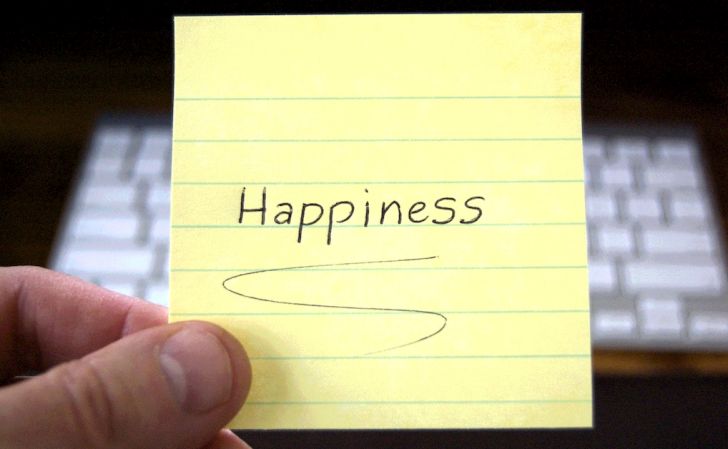
ミルの観点からすると、自由とは、個人が自分固有の幸福を追求するための条件であり、それによって一般福祉を向上させ、社会全体の幸福を向上させるための条件だ。この点から思想や言論、行為の自由が“要請”される。なので、他者の幸福追求ゲームを阻害する自由を承認することはできない。
ところで、自由についてはドイツ観念論者として知られるヘーゲルも論じていた。
観念論と聞くと、何だか訳の分からない観念についてあれこれ論じているんじゃないの?と思うかもしれない。確かにそうした点はあるにはある。が、『法の哲学』で展開されている自由論は、近代哲学のひとつの頂点をなしていると言っても過言ではない。
ヘーゲルは『法の哲学』で次のように述べていた。
初め、子供の意志は、ただ自分の内面において自由を確立しようとする。しかしその自由は恣意でしかない。意志が自分の自由を実質的なものへと転化するためには、思考を通じて、自分の衝動を幸福へと結びつけるための手段を検討する必要がある。そのため、教養による陶冶が自由の実質化のために不可欠なのだ。
制度としての自由が整備された一方で、私たちは自分の幸福が何であるかを自分で考えなければならなくなった。そのために役立つのが教養だ。私たちは教養を身につけることによって、何が自分にとっての幸福であるかを吟味することができるようになる。そうヘーゲルは論じる。
自分にとって本当に「よい」ことは何か、何が自分固有の幸福であるかを規定する能力がなければ、ただ単に自由を与えられても、それは価値をもたない。自分にとって本当に「よい」ことは何かをつかんでいなければ、個性を発揮することもできない。これは実感として納得できるひとも多いだろう。
とはいえ、ミルの議論は、自由をイデオロギー的に絶対視する見方とは一線を画している。私たちはミルの議論を、功利性の原理からたどり直し、それがどの程度妥当であるかをみずから吟味検討できる。この検証可能性は思想が備えていなければならない条件のひとつであり、その思想が普遍的かどうかを判断するための重要な判断基準だ。
- sciondriver (CC BY-NC 2.0; modified)
- Tallapragada (thumbnail, CC BY-NC 2.0; modified)

