
『行動の構造』は、フランスの哲学者モーリス・メルロ=ポンティ(1908~1961)のデビュー作だ。1942年に出版された。
メルロ=ポンティは、フッサールの現象学をベースに、ハイデガー的な実存論を取り入れることで、独自の実存論哲学を打ち立てた。本書でメルロ=ポンティは、主著の『知覚の現象学』に先立ち、既存の知覚論・身体論に対する批判を加えつつ、私たちの身体を「実存」というキーワードによって論じている。
実存の概念は、哲学者の間で微妙にニュアンスが変わってくるが、メルロ=ポンティでは、「ありうる」を目がけることをいう。つまり身体は「ありうる」を目がけるための条件だと考えるのだ。
言われてみれば、確かにそんな気がするかもしれない。だが重要なのは、このメルロ=ポンティの主張が、どのようなコンテクストにおいてなされたのかということだ。
身体と精神の関係について
身体が実存の条件であることは、決して自明ではない。というのも私たちは普段、身体は頭、胴体、手足といった部位からなる統一体、有機的メカニズムとみなしているからだ。
身体は物理的なモノであり、精神(意識)とは別に存在している。これがごく自然な見方だ。だが身体は、モノのように、自分の外にあって触ったり動かしたりすることができるわけではない。また、意識のようにありありと現れているわけでもない。私たちの身体は、事物と異なる独自の性質をもっているのだ。
自然科学の発展により、近代以降、人間が神の被造物であるという観念は次第に薄れてきた。また、身体のメカニズムが明らかになるにつれ、身体はそれ自体の秩序をもっていることが分かってきた。その結果、次のような問いが生まれてきた。――意識と身体は一体なのか、分離しているのか。相互に無関係なのか、あるいは相互に影響を与えているのか。

意識と身体の関係についてのこうした問題は、心身問題という形を取って論じられた。デカルトやスピノザ、ライプニッツといった近代哲学者のほか、ラ・メトリのような唯物論者もまたこの問題に取り組んだ。
ラ・メトリは、デカルトの心身二元論を踏まえ、人間の精神は脳の働きから生じ、人間はそれによって動かされる機械であると説いた。一見、とっぴな考え方に思えるかもしれないが、実際はそういうわけでもない。
脳を最高位とする中枢神経系からの信号を受けて、身体の各部位は動作する。意識は脳における信号伝達から生じ、身体は中枢神経を中心とする命令系統として成立している。こうした規定は現代において一般的なものだが、ラ・メトリの洞察と、本質的には同じものなのだ。
では、メルロ=ポンティはこういった問題について、どのように考えているのか。以下、その点について見ていこう。
反射学説批判
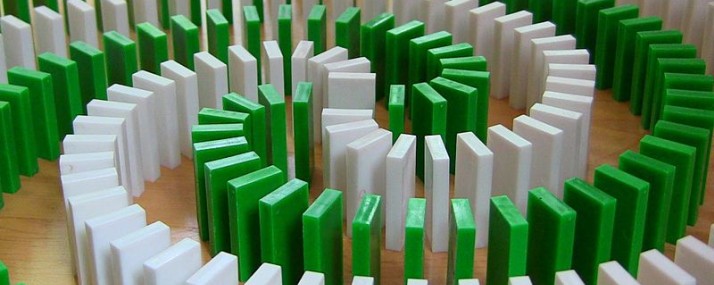
メルロ=ポンティは本書で、身体が脳からの信号を受けて動作するパーツの集合体であるという見方を批判する。そうした見方を、メルロ=ポンティは反射学説と呼ぶ。
古典的な行動論は反射学説として展開した。反射学説のポイントは、刺激が反応を生み出すという構図にある。常識的な見方では、私たちは何かを見るために目をそちらのほうに向けるとされる。だが、反射学説的には、その「何かを見るため」ということもまた、反射の結果と位置づけられるのだ。
メルロ=ポンティによると、反射学説では、一切の反応は、先行する刺激によって規定されているとされる。これは要するに、ちょうどドミノ倒しのように、刺激と反応は、数珠つなぎの要領で因果連鎖をなしているということだ。
知覚は刺激と反応の因果関係によって成立する。これと同様に、行動もまた、もろもろの部分から構成されるプロセスとして規定される。何らかの意図があるように見えるとしても、あらかじめ神経系の活動によって調整されているにすぎない。一切の行動は、因果連関として捉え直すことができる。これが反射学説の基本的なスタンスだ。
メルロ=ポンティは、そうした見方に異を唱える。
反射の過程を要素に分解することはできない。事実、刺激と反応のどちらが最初かは言うことはできない。なぜなら、行動が環境の結果であるとも、環境が行動の結果であるとも言えてしまうからだ。対象が見えるためには、まずもって対象の方を向いていなければならない。
こうした事情から、反射学説の擁護者たちは、反射回路なるものを想定した。
人間の体内には、刺激に対する反射を抑制、逆転するような条件があり、人間の場合は、特に一切の反射について大脳と小脳が介入する。神経系に2段階の階層構造があり、反射回路のうちで生じる「反射の複合」では、特定の反応が生じるときに、他の一切の反応は制止されているのだと主張された。
だが、こうした反射回路は、経験と理論の一致を覆い隠すために持ち出されてきたにすぎない。
反射を禁止する制止装置を神経系内に仮定する必要など存在しない。このことは、例えば、体のかゆいところをかくことを考えてみれば分かる。私の手が右に伸びているか、あるいは左に伸びているかに応じて、筋肉を収縮させる程度は大きく異なってくる。それゆえ、かゆい箇所につながる神経回路があらかじめ準備されていると想定することには無理がある。
そこで反射学説では「知性」の概念が導入された。だがそうすると、右手の位置を特定し、左手が右手のかゆい箇所に達するまでにどのような経路を通らなければならないかについて、あらかじめ計算し測定しておかなければならないことになってしまう。
反射学説には無理がある。これがメルロ=ポンティの第一の結論だ。
では、行動はどのように生じているというのだろうか。
メルロ=ポンティによると、行動は第一に、空間のうちで生じる。ただし、ここでいう空間は、等質な物理学的空間ではない。それは身体と結びついた「状況」である。行動は物理学的空間ではなく、個々にとっての「状況」においてなされる。このことは人間だけでなく、動物一般にとって当てはまる。そうメルロ=ポンティは考えるのだ。
では、状況のうちで、行動はどう生じるのだろうか。この点を考えるために、次に、行動の構造に関する議論を確認することにしよう。
行動の構造
構造と聞くと、身体の部位の動かし方のほうに目が向きそうになるかもしれない。だが、それは行動のひとつの要素ではあっても、構造ではない。というのも、私たちが行動と呼ぶ現象は、必ずしも因果法則によって規定されているわけではないからだ。
たとえばニーチェは『道徳の系譜』で、良心を「約束を守る能力」と規定している。私たちは誰からも命令されることなく、また負い目や罪の意識に影響されることなく、自分の意志で、自分が「よい」と思うことをなすことができる。あるいはそこに人間としての自由があると了解している。カントは『実践理性批判』で、忠士は信頼する君主の命令であれば、自分の命さえも犠牲にすることができるとしている。だがその意味は、忠士はおそらく死を選ぶだろうということではなく、死を選ぶ可能性があると確信するとき、みずからの自由を了解するということだ。
メルロ=ポンティが反射学説を批判する際に考慮しているのはこうした事情だ。つまり人間は、既存の法則(自己保存の法則など)に従うよう設計されている存在ではなく、「ありうる」に向かって行動する可能性をもつ存在であると考えるのだ。
このことをメルロ=ポンティは次のような言い方で表現している。つまり、行動は本質的には、「状況」において規定されつつ、実存としてなされるものである、と。
ここでいう「状況」とは、物理学的な時間・空間のことではない。動物がひとつの主体として、そのうちに「住まっている」ところの、生きられているところの環境世界のことをいう。分かりやすくいうと「私にとっての世界」がここでの状況のことだ。
以上を踏まえて、次に、メルロ=ポンティによる行動の構造の区分を見てみよう。メルロ=ポンティは本書で、3つの類型を示している。
- 癒合的形態
- 可換的形態
- 象徴的形態
この区分の基準は、状況における被規定性と、状況を編み変える自由の間のバランスにあると考えるのがいい。つまり、癒合的形態は行動が状況によって規定されていることをいい、逆に、象徴的形態は行動が状況を規定していることをいう。
これは言いかえると、たとえ癒合的形態においても、行動は刺激-反射の因果的連鎖のうちで生じるわけではないということでもある。いかなる動物の、どのような行動であっても、状況のうちで自由である。このことは、不随意的な動作(くしゃみなど)は行動とはいえないということも意味している。
癒合的形態
癒合的形態では、行動は自然のうちの生存状況、生存条件のうちに限定されている。
メルロ=ポンティは、アリを使った例について以下のように言っている。「棒のうえに置かれたアリが、黒い円を記された白紙のうえに降りるのは、白紙が一定の大きさをもち、地面への距離、棒の傾きが一定の値いをもつときだけ」である、と。
確かに、自分の巣に帰る途中のアリが、前に大きな水たまりがあるとき、そこに突撃するような光景を見たことない。実験したわけではないので断言できないが、水たまりを沿うなど、何らかの仕方で巣への新しい道を探しているはずだ。
可換的形態
次の可換的形態は、構造化された知覚に基づく行動のあり方を指している。
メルロ=ポンティによると、こういう実験がある。
ニワトリに訓練を施して、薄い灰色(グレー1)の標識がある穀物を選び、少し濃いめの灰色(グレー2)の標識のほうは放っておくようにしつける。その後、グレー2の標識を、グレー1よりも薄い灰色(グレー0)の標識と交換する。
ここで、もしニワトリが色そのものに反応するのであれば、変わらずグレー1の標識のほうに反応するはずである。だが実際には、ニワトリはグレー0の標識を選ぶ傾向にあった。
この実験が示しているのは、状況のうちで濃淡の知覚が構造化され、濃淡がひとつの「意味」として知覚されており、それに即して行動がなされるということだ。
仮にもし、対象の色彩が神経を刺激し、その反応として行動を引き起こすことが法則であるならば、学習は起こりえない。これは言いかえると、ニワトリは何ら新しい状況に対応できないということだ。実験以前まで、ニワトリはグレー2の標識について知らなかった。もし刺激と反射の法則が特定の行動を引き起こしたと論じたいのであれば、未知の選択肢に対して反応する回路が、ニワトリに前もって備わっていたことを証明する必要がある。だが、もしそうであれば、しつけるというプロセスがそもそも不要だったはずだ。
法則を選択して適用する能力が先行的に備わっているという考え方に、反射学説一般の困難がある。この点については、先ほどのメルロ=ポンティによる批判にある通りだ。
可換的形態は、癒合的形態と比べると、知覚のより複雑な構造化に基づいている。だがメルロ=ポンティによると、それは人間の行動の構造であるわけではない。というのも、可換的形態では、対象は個々の状況のうちに“はめ込まれて”おり、動物はその対象を一般的な視点から捉えることができないからだ。対象を一般的な時間・空間、物理的な座標系のうちに置き直すには、そのための客観化能力を必要とする。そこに人間の行動と、動物の行動の違いがあるという。
だが、それはひとつの違いでしかない。
人間は動物と異なり、行動それ自体を変えることができる。ある目標を夢とし、それを目がけて身体性を変える可能性をもつ。その可能性は、動物には存在しない。メルロ=ポンティはここに、実存としての人間の独自性を見る。メルロ=ポンティが象徴的形態という概念で言い表そうとしているのは、その独自性にほかならない。
象徴的形態
第3の行動の構造は、象徴的形態だ。
ここでメルロ=ポンティが取り上げている例は、タイプライターによるタイピング、そしてピアノ演奏だ。
日常的にパソコンを使っていれば分かるはずだが、キーボードで文字を入力する際、最初のうちはキーを見ないとタイプすることはできない。だが段々慣れてくると、目をつぶっても入力できるようになる。いちいちキーの並びを思い出しつつ、タイピングを行っているわけではない。そのとき、タイピングは一連の動作として構造化されているからだ。
チンパンジーの行動においては、手段はともかく、主題が、種のア・プリオリによって固定されたままであった。刺戟を刺戟そのものとして表わし、物の固有の真理と価値とに開かれ、〈意味するもの〉と〈意味されるもの〉、〈志向〉と〈その目指すもの〉との充全な合致へ向かう行為は、象徴的形態とともに現われる。ここでは行動はもはや単に一つの意味を〈もつ〉のではなく、行動そのものが〈意味〉なので〈ある〉。
動物は自己を対象化できず、与えられた状況から抜け出ることができない。これに対し、人間は、自分の行動を振り返り、それに対して態度を取ることができる。これは動物には見られない、人間独自の性格である、とメルロ=ポンティは考えるのだ。
行動するとは「実存」すること

行動はその瞬間から即自の秩序を離れて、有機体が外部に対して行なう内的可能性の企投となるわけである。
メルロ=ポンティが反射学説を批判したとき、その根拠には、行動が新たな状況を目がける「企投」としてなされるという洞察があった。行動は「いまある」世界の秩序のうちに限定されているものではない。それは「ありうる」を、つねに繰り込みながら行われる。
これを言いかえると、行動は世界に対する態度であり、「ありうる」を目がけることでもある。行動は自然法則に従って生じるのではなく、世界のほうが生物の態度によって分節化される。それが状況のうちにおける行動の自由ということの意味だ。
では、こうした洞察からどのような視野が開かれてくるのか。メルロ=ポンティは、本書の後半で次のように論じている。
人間的行為は、それに方向を与える実践的な意図のもとで、相互に連関する。それゆえ、行為の目的と手段を別々のものとして区別することはできない。このとき、問題が転換される。すなわち、着目すべきポイントが、行為の目的と手段の分析から、行為のもつ意味とその内的構造の分析へと変わるのだ。
後者の観点からすれば、「生活」なるものが人間独自の意味をもつことも理解できるだろう。たとえば衣服は、私たちを雨風から守ってくれるという機能をもつ。だが衣服を着るという行為は、着飾る行為として、自分自身や他人に対して新たな態度を示すものでもある。
このように「ありうる」を目がけること、「いまある」構造を超え出て別の構造を作り出す能力をもつこと、ここに人間の人間性がある。そうした能力があるからこそ、私たち人間は言葉を使ったり、可能性に絶望して自殺したり、あるいは可能性に賭けて革命運動へと身を投じたりすることさえできるのだ。
人間労働の意味は、現実的環境の向こう側に、各自が多くの局面から見ることのできる一つの〈物の世界〉を認め、そして無限な空間・時間を占有するということである。そして言葉とか自殺とか革命的行為などの意味するところも、みな同じものだということは、容易に証明されうるであろう。
人間の行動を考えるということ
もちろん、1942年に刊行された本書の議論をそのまま受け取ることはできない。反射のメカニズムについても、現代の心理学では、はるかに多くのことが分かっているはずだ。
しかし、私たち人間の行動の意味や価値を考えるにあたって、そうした分析の進展は、ほとんど影響を与えない。そのためには、身体を物理的メカニズムとして捉える視点とは、別の考え方が必要となる。この点からすると、メルロ=ポンティは確かに優れた洞察を示していると言っていい。
行動を刺激と反射の連関に解消することはできない。それは状況のうちにおける構造として構造化されている。動物はその構造を客観的に捉えて変化させることができないが、人間はそれに対して態度を取ることができる。私たちの行動はたえず「ありうる」構造を「いまある」構造に繰り込むことによって成り立っている。人間の行動を考えるとは、これがどのようにして起きるか、どのような条件で私たちが「ありうる」を目がけるようになるのかを明らかにすることである。
「ありうる」を目がけること。これは別の言葉で言うと、創造性のことだ。

二足歩行ロボットの「ASIMO」がダンスを踊っているシーンを見たことがあるひともいるだろう。バランスを崩さず、軽快に飛びまわる光景は、私たちにある種の感動を呼び起こさせる。
だがその感動は、決して、ダンスそれ自体が芸術的に優れているので生まれてくるというのではない。ASIMOのダンスは、ちょうどよく訓練された猿回しのように、メルロ=ポンティのいうところの可換的形態を超えない。
では、なぜ私たちはその光景に感動を覚えるのか。それは、私たち人間がロボット開発の歴史において前人未到の境地に達したことを象徴的に示しているからだ。ASIMOがダンスしようがバク転しようが、そのことは感動のもとではない。人間の知性が、さらなる「ありうる」の領域へと一歩を踏み出したことが感動の本質的な理由なのだ。
このことはASIMOだけではなく、芸術やスポーツにも当てはまる。なぜ芸術やスポーツにおいても、私たちは心を動かされるのか。それは、「いまある」を超え出て「ありうる」を目指す可能性が、人間の実存を生かしている「核」であるからだ。
メルロ=ポンティの議論を受けて、次のように言ってみたい。
ピアノが上手く弾けなければ、練習して上達することができる。だが、練習すれば必ず上達するというわけではない。誰でもプロのピアニストになれるわけではない。しかし、だからこそ、私たちは努力したり諦めたり、夢や希望を抱いたり絶望したりするのだ。もし誰でもプロのピアニストのように弾けるなら、それは単なる指の動作にすぎない。その際、ピアノを弾くことは無意味となる。行動そのものが意味であるとはそういうことだ。
私たちは、指の構造を分析することで、ピアノを上手く演奏するための方法を示すことができる。しかしそのことは、私たち一人ひとりの生にとってピアノを弾くこと、練習することがそもそも何を意味するか、どのような価値をもつかについては説明しない。なぜ辛い練習に耐えてまで、ピアノを弾きつづけようとするのか。こうした問いに対して答えようとするなら、私たちの実存と欲望のあり方を見つめなければならない。こうした観点を導入したのは、哲学史上、メルロ=ポンティがほぼ初めてだ。
- http://www.philosophical-investigations.org/Users/PerigGouanvic (CC BY 3.0; modified)
- Escalhuda (CC BY-SA 3.0; modified)
- Frederik Magle (CC BY-NC-SA 2.0; modified)
- Momotarou2012 (CC BY-SA 3.0; modified)
- http://www.philosophical-investigations.org/Users/PerigGouanvic (thumbnail, CC BY 3.0; modified)
